
トキナーのMFレンズFiRIN(フィリン)20mm。発売された時に購入を検討したが結局買わなかったレンズ。
なぜ今持っているのかというとこちらのブログで投げ売りされているとの情報を見て「この価格(2万円台)なら」と購入した。
このスペックのレンズはFE20mmF1.8Gを既に所有しているので必要ないと言えばないのだが、比べてみて使いやすい方を残せばいいかなと。
なお、私が入手した品には軽い曇りがあった。


格安セール品だから、こういうこともあるかと諦める。
近距離LEDの強光で照らすから見えるだけで天井の蛍光灯にかざしても見えない程度の曇りだし。
厳しめのお客さんから返品された品がメーカー基準的には問題なしでもう一度市場に出てくる、みたいな流れがあるんじゃないかと想像する。

20mmF2というスペックの割には小さい。
重さはそこそこあるが、こういうレンズはそれなりの重さがあった方が高級感とか信頼感に繋がるから悪いことでもない。
ピントリングの操作感も適度な重さがあって良い。

書体がちょっとおしゃれだ。ライカを意識したのかもしれない。
では、性能について。

解像力は絞り開放から十分。


中央はもちろん周辺も十分。重箱の隅をつつくレベルで言うと四隅は僅かに像ブレが感じられる。
だが、これも少し絞れば解消する。↓

これは5,000万画素の写真をピクセル等倍レベルに拡大した、非常に厳しい基準での話なのであまり気にしないでほしい。
普通に使う分には、このレンズは絞る必要がない。どんな場面でも開放で撮影できる。

上隅を見ると僅かな歪曲収差があるのが分かる。
これは現像ソフトで簡単に補正できる(↓ここでは周辺減光も合わせて補正している)。
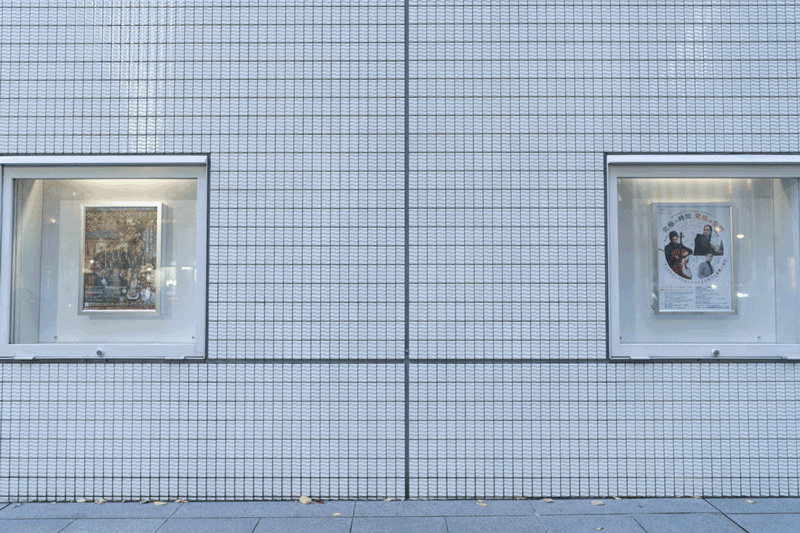
↓こういう写真の場合は、補正なしだと若干気になるかもしれない(左上)。

ボケ量はそれほど期待できないが、ピントを近めに置いて背景を遠く離せば一応ボケる。

中央部分はきれいにボケる。玉ボケの内側に模様があるが私はあまり気にしない。

周辺は形が崩れる。

太陽に向けると割と簡単にゴーストが発生する。広角レンズだしまあこんなもんだろう。

作例


季節感のない写真の羅列になってしまい申し訳ない。

一眼レフカメラだと20mmは相当な広角というイメージがあるかと思うが、実際に使ってみると広角感はそこまで強くない。
パースがつかないように気を付ける(カメラを上下に傾けない)と標準レンズっぽい写真が撮れる。

東京の音羽を散歩している時に撮った写真。
↓この写真左側の建物。こういう狭い路地で、距離を取れない状況でも写真にできるのが広角レンズのいいところ。


この学生寮の建物がなぜか気に入っている。

カメラを上に向けて建物を撮るとパースがついて広角レンズっぽさが出てくる。

これは目白あたりで撮った写真。看板の文字と模様が調和していておもしろいと思った。
読めないから模様と感じるのであって読める人だと感じ方が違うのかもしれない。

これは横浜関内の吉田町。
意識して配置したわけではないのだろうけど、なんか絵になってる感じがすごいなと思った。


























